100 Ωの抵抗に周波数60 Hz、実効値√2 Aの正弦波電流を流した。正しいのはどれか。
1: 141 Wの電力が消費される。
2: 正弦波電流の振幅は1 Aである。
3: 正弦波電流の周期は20 msである。
4: 抵抗両端の電圧の最大値は200 Vである。
5: 正弦波電流と抵抗両端電圧の位相は![]() radずれる。
radずれる。
正弦波交流回路とは、電圧や電流の振幅が時間と共にプラスとマイナスを行ったり来たりする波形を出力する回路である。
交流(AC)とは、時間の経過とともに、電圧や電流の振幅の大きさが交互(プラスとマイナス)に変化する波の事をいいう。主に正弦波といわれる波形のことを交流というが、三角波のように三角形をしていようが、方形波のように長方形をしていようが振幅の大きさがプラスとマイナスとを行ったり来たりしている形ならどれでも交流として扱う。但し、波の形になっていてもプラスとマイナスを行ったり来たりしていない波は直流として扱うため注意。
交流を作るためには、4つの項目が必要となる。
①振幅の最大値、②波形の形、③波形が変化する速さ、④位相である。
振幅が最大となるときの値が最大値であり、 最大値 = √2 × 実効値 で表される。
実効値は、 実効値 = 最大値/√2 、 平均値は 平均値 = 2 × 最大値/π で表される。
位相とは、波形の時間的なズレのことをいい、波形のズレ方によって同位相、遅れ位相、進み位相がある。
また、交流には周波数と周期との関係もある。
周波数(f)とは、1秒間に何回プラスとマイナスを行ったり来たりするのかの波の回数のことで、
周期(T)とは、1回あたりの変化に必要となる時間のことである。
周波数と周期の関係は、 f = 1/T となる。
交流電力には、皮相電力、有効電力、無効電力があり、それぞれ下記のように定義されている。
①皮相電力S:電源から送り出される電力[VA] → 皮相電力S [VA] = 電圧 × 電流
②有効電力P:負荷で消費される電力[W] → 有効電力P [W] = 電圧 × 電流 × cosθ
③無効電力Q:負荷と電源間を往復するだけで消費されない電力[var] → 無効電力Q [var] = 電圧 × 電流 × sinθ
抵抗に交流電源が接続された回路の場合、「電圧」と「電流」が同位相(位相差0℃)になる。
コイルに交流電源が接続された回路の場合、「電圧」に対して「電流」が90℃遅れ位相になる。
コンデンサに交流電源が接続された回路の場合、「電圧」に対して「電流」が90℃進み位相になる。
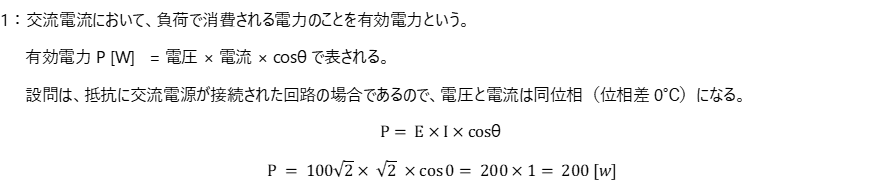
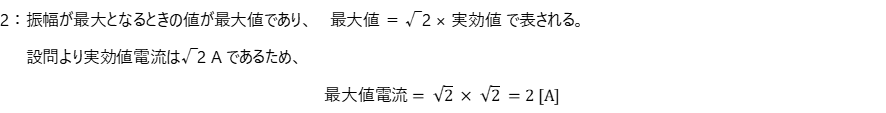
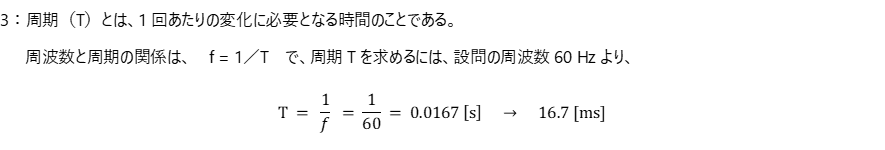
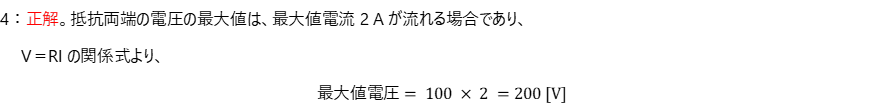
5:抵抗に交流電源が接続された回路の場合、「電圧」と「電流」が同位相(位相差0℃でズレなし)になる。
